お問い合わせ

webからお問い合わせ

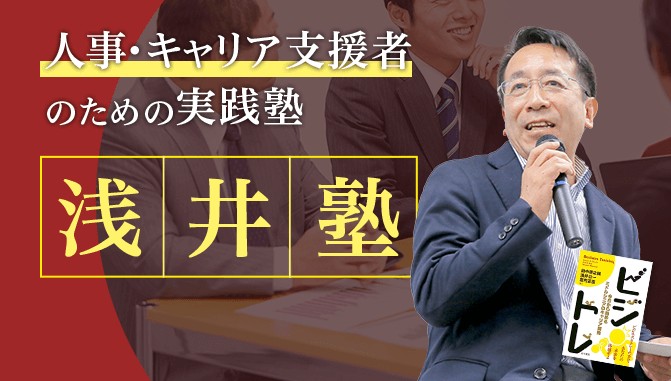
キャリアコンサルタントに関するコラムや最新情報など随時更新しています。
人的資本経営
2025.09.17

建設業界の中小企業は、地域のインフラ整備や住宅建設を支える重要な役割を担っています。
しかし、その多くは大手ゼネコンや発注者からの下請・受託事業に依存しており、 社員の意識や働き方に 「指示を待つ」「言われた通りにやる」 という受身の姿勢が染みついています。
もちろん受託構造の中で品質や納期を守ることは重要ですが、過度な受身姿勢は社員の主体性や成長意欲を削ぎ、 長期的には組織の競争力低下につながりかねません。
①大手ゼネコンからの指示依存
元請けの指示が優先されるため、社員が自分で考えて動くよりも「言われたことを確実にやる」ことが評価されやすい。
②育成リソースの不足
現場も経営層も多忙で、若手に主体的な挑戦を促す機会が限られる。結果として「自分で考えない」習慣が固定化。
③キャリアの閉塞感
中小規模のためキャリアパスが狭く、「ここでどんな成長ができるのか」が見えにくい。受身のまま年次を重ねてしまう。
①若手の成長停滞
「言われたことをやるだけ」で達成感が薄く、やりがいを失いやすい
②中堅層のマンネリ化
改善や提案の習慣が育たず、「変わらない現場」に安住
③経営力の低下
主体性の欠如が積み重なり、変化に対応できない組織体質へ
中小企業だからこそできる「社員の主体性を引き出す仕組み」が必要です。
①キャリア面談で主体性を引き出す
「自分はどんな現場で強みを発揮できるか」「どんな挑戦をしたいか」を言語化する場を設ける
③小さな改善提案を評価する文化
現場の安全や効率化に関するアイデアを積極的に拾い、提案を評価対象にする
③越境的な学びの機会
他社や異業種との合同研修、外部セミナー参加を奨励し、受身姿勢から視野を広げる
「辞めない組織」から「伸びる組織」への転換を実現した事例です。経営課題としての人材定着をどう解決したのか、そのプロセスをご覧ください。
■ 事例①:地方建設中堅C社
C社では「元請けの指示待ち」が当たり前で、若手社員が成長実感を持てませんでした。そこで年1回のキャリア面談を導入し、「自分のやりたいこと」を棚卸しする場を提供。さらに現場改善のアイデアを評価制度に反映した結果、若手の改善提案件数が3倍に増加しました。
■ 事例②:地域工務店D社
D社では、社員が受身で現場を回すだけになり、技術継承が進まない課題がありました。そこで外部研修に社員を派遣し、学んだ知識を社内で共有する仕組みを導入。結果として「自分が会社に貢献できる」という実感が生まれ、中堅社員のモチベーションが大幅に向上しました。
“個別相談会”を開催(まずはお気軽に)
「自社だと何から手を付ければいい?」「用語の意味は分かったけれど、運用に落とすイメージがまだ…」という方へ。
HRラボでは1社ごとの個別オンライン相談(30〜45分)を承っています。建設はもちろん、製造・医療・IT・サービスなど、どの業界でもご利用いただけます。
専門用語の整理から、現場のモヤモヤの言語化まで丁寧にお伺いします。
<お問い合わせフォーム>
下記よりお申し込みください。担当より日程候補をご連絡します。
HRラボ お問い合わせフォーム
中小建設業に根付く「受身の姿勢」は、現場の安定には寄与しますが、社員の成長やキャリア自律を阻害する大きな壁でもあります。
キャリア面談や小さな提案制度、越境的な学びの機会を通じて「受身を脱し、主体的に動ける社員」を育てることが、中小建設企業の未来を守る活躍支援のカギとなるでしょう。
#建設業 #中小企業 #受身の姿勢 #キャリア支援 #主体性 #人材活躍 #HRラボ #人材育成 #組織開発
1

2

3