お問い合わせ

webからお問い合わせ

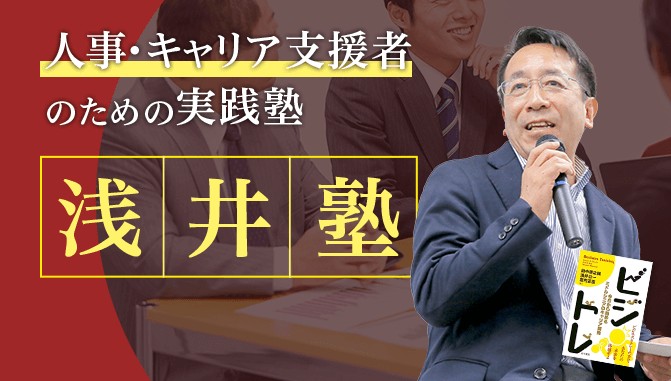
キャリアコンサルタントに関するコラムや最新情報など随時更新しています。
人的資本経営
2025.10.09
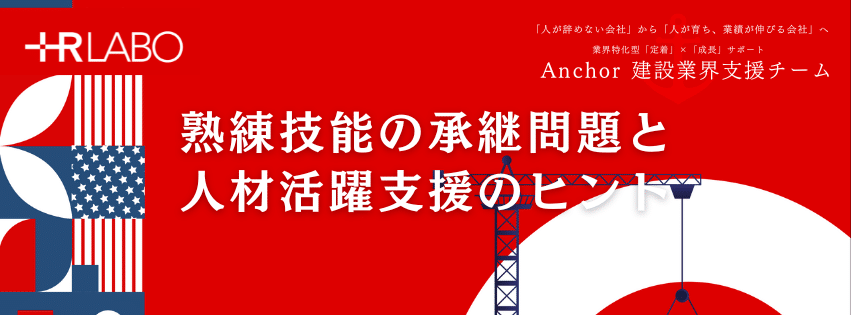
日本の製造業は、長年にわたり熟練社員の技能と経験に支えられてきました。しかし今、その土台が揺らぎ始めています。 大量退職期を迎えるベテランの技をどう次世代に承継するかが、品質維持や競争力強化の分水嶺となっています。 技能が暗黙知のまま失われれば、現場力は弱まり、生産性や信頼性に直結するリスクが高まります。 だからこそ、従来の「背中を見て学ぶ」文化から、仕組みによる承継・DX活用へと転換することが急務です。
目次
製造業大手は、日本のものづくりを支えてきた中核的存在です。しかし今、深刻化しているのが熟練技能の承継問題です。長年にわたり現場を支えてきたベテラン社員の高齢化と大量退職が進む一方で、若手への技能継承が思うように進まず、品質や生産力の維持に大きなリスクを抱えています。
経済産業省『ものづくり白書2025』では、技能承継の遅れは製造業全体の競争力を低下させるリスクとして繰り返し指摘されています。さらに労働政策研究・研修機構(JILPT)の調査でも、「指導者不足」「教育リソース不足」が製造業における人材育成の主要課題として明らかになっています。
技能の暗黙知化
熟練者は「勘」や「経験」に基づいて判断することが多く、作業の多くが暗黙知のまま残されています。マニュアル化が難しく、若手が学ぶ場が限定的になっています。
若手の経験不足・定着難
技能習得には時間がかかりますが、若手が一人前になる前に離職してしまうケースが目立ちます。厚労省「若年者雇用実態調査」でも、技能職における離職理由として「成長実感の不足」が上位に挙げられています。
教育リソースの不足
現場は生産優先で動いているため、熟練者が教育に割ける時間は限られています。結果として、OJTはあるものの体系的な教育は不十分で、若手が成長を実感しにくい状況が続いています。
テクノロジーと技能のギャップ
DXや自動化の進展とともに、熟練技能と新技術を融合させる設計が追いついていません。その結果、「技能」と「テクノロジー」が並行して存在するだけで、相乗効果が得られていないのです。
熟練技能の承継を放置したままにすると、製造業大手は目に見える形でも潜在的な形でも複数の深刻リスクに直面します。
品質不良や不具合の増加による顧客信頼の低下
熟練者のノウハウが後継者に伝わらず、現場判断の精度が低下すれば、不適合品や欠陥品の発生率が上がります。顧客クレーム対応コストやブランド毀損が増大し、信頼を失う危険性があります。
技能の空洞化による生産性低下・競争力喪失
技能承継が進まなければ、ライン調整や工程改善の精度が落ちます。改善提案や効率化のアイデアも減り、競合との差別化は難しくなります。
若手が「学ぶ機会がない」と感じ、離職が加速
教育環境が整っていなければ、若手は「ここにいても成長できない」と感じやすく、早期離職につながります。厚労省の調査でも、若年層の退職理由に「キャリアの見通しのなさ」が挙げられています。
海外拠点での技能教育が進まず、グローバル展開に支障
グローバル化が進む中、現地スタッフへの技能伝達は必須ですが、国内で承継が進まなければ教育は海外に広がりません。結果として、拠点間の品質格差や納期遅延が発生しやすくなります。
これらのリスクは短期的には顕在化しにくいですが、5〜10年スパンでは企業の競争力と存続を脅かす重大課題です。
熟練技能を若手に着実に継承し、組織全体の技能力を底上げするには、制度・文化・技術を組み合わせた包括的な仕組みが必要です。
技能の可視化・教材化
熟練者の作業プロセスを動画、センサーデータ、コメント付きマニュアルとして記録。若手が繰り返し学べるデジタル教材にすれば、自主学習と反復練習が可能になります。JILPT「ものづくり産業の人材育成調査」でも、OJTの普及率は高い一方で教材化・DX活用が遅れていることが指摘されています。
メンター制度による継承
熟練者を「教育リード役(メンター)」として明確に位置づけ、若手とペアで技能を学ぶ体制を整えます。質問や試行錯誤がしやすい環境をつくり、さらにメンター自身に評価や報酬インセンティブを付与することで、継承活動を持続可能にします。
キャリア面談で成長を振り返る
キャリア面談で「どの技能を習得したか」「次に挑戦すること」を言語化させることで、若手は自分の成長を実感できます。面談結果を管理職や経営層と共有すれば、配置転換や教育計画に反映でき、組織全体で技能承継をマネジメントできます。
DXとの融合
IoTやAIで熟練者の動作データを収集・分析し、暗黙知を形式知化。これにより標準化・自動化が進み、若手の学習コスト削減と現場精度向上を両立できます。製造業のDX推進調査でも、「人材育成とデジタルの融合」が成長企業の特徴として挙げられています。
複合プログラムの設計
単一施策では効果が限定的です。教材化 → メンター指導 → 面談 → DX分析といったサイクルを「技能承継プログラム」として統合すれば、学びと挑戦が継続的に循環する仕組みを築けます。
事例①:大手製造業 Q 社
Q社では溶接や組立の熟練技能承継が課題でした。技能動画教材を制作して若手が繰り返し学べる仕組みを導入し、キャリア面談で習得度を確認。結果、若手技能試験の合格率が大幅に向上しました。
事例②:製造大手 R 社
R社ではベテランの大量退職を前にメンター制度を導入。熟練者を教育担当に据え、若手と二人三脚で現場に入りました。さらにAIで作業データを分析し、暗黙知を形式知化。その結果、品質不良率が前年比30%減少し、承継が経営成果に直結しました。
キャリコンサロン製造業界超雑談会
製造業の人材育成・キャリア支援をテーマに開催。現場のリアルな声を共有しました。
レポートはこちら
“個別相談会”を開催(まずはお気軽に)
「自社だと何から手を付ければいい?」「用語の意味は分かったけれど、運用に落とすイメージがまだ…」という方へ。
HRラボでは1社ごとの個別オンライン相談(30〜45分)を承っています。建設はもちろん、製造・医療・IT・サービスなど、どの業界でもご利用いただけます。
専門用語の整理から、現場のモヤモヤの言語化まで丁寧にお伺いします。
<お問い合わせフォーム>
下記よりお申し込みください。担当より日程候補をご連絡します。
HRラボ お問い合わせフォーム
製造業大手における熟練技能の承継問題は、品質・生産性・競争力に直結する重大課題です。重要なのは「現場で背中を見て覚える」から「仕組みで学び、DXと融合させる」への転換です。
キャリア面談やメンター制度を通じて若手が成長を実感しながら技能を承継できる環境を整えること。それが未来のものづくりを支える人材活躍支援のカギとなります。
1

2

3