お問い合わせ

webからお問い合わせ

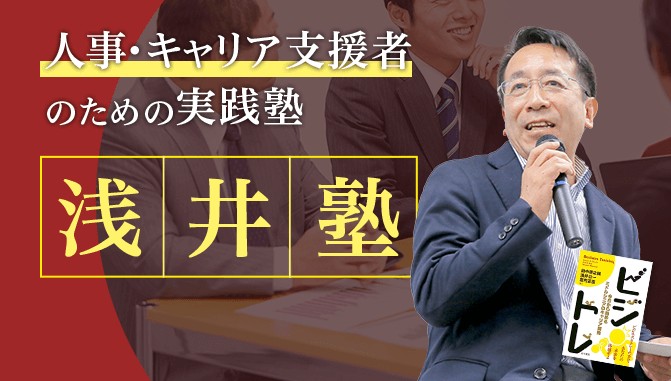
キャリアコンサルタントに関するコラムや最新情報など随時更新しています。
人的資本経営
2025.10.01

採用には成功しているのに、数年後には“与えられた業務をこなすだけ”の若手社員が増えてしまう。多くの製造業の人事担当者が抱えるこの悩み。
背景には、年功序列や失敗を許容しない風土といった製造業特有の文化があります。このまま放置すると、若手はキャリアを描けず挑戦しないまま中堅化し、組織の変革力が弱まってしまいます。
本記事では、若手の挑戦不足を解決するキャリア面談・越境学習・挑戦を評価する仕組みづくりについて、事例を交えて解説します。
目次
製造業は依然として日本経済の屋台骨であり、大手企業は技術革新と安定雇用の両輪を担ってきました。しかし現場では、「若手が挑戦しない」「自分のキャリアを主体的に描こうとしない」という声が年々強くなっています。
採用活動においては新卒・第二新卒の確保に成功している企業も多いものの、その後のキャリア形成段階で停滞が見られます。意欲を持って入社した若手が、数年以内に「言われたことしかできない人材」になってしまうケースは珍しくありません。
経済産業省『ものづくり白書2025』でも、人材育成の不足やキャリア意識の低下が製造業全体の競争力を阻害するリスクとして繰り返し警告されています。さらに、労働政策研究・研修機構(JILPT)の調査によれば、企業の多くが「人材育成の重要性を認識しているにもかかわらず、十分な投資が行えていない」と回答しており、現場と経営の認識ギャップが浮き彫りになっています。
この問題を放置すれば、目先の生産性は維持できても、中長期的なイノベーション創出力の低下や、グローバル競争への対応力不足といった経営上のリスクに直結します。
年功序列文化の残存
依然として「勤続年数」や「上司の主観的評価」が重視される評価制度が残っています。この構造の中では、若手が果敢に挑戦してもその努力が正しく評価されにくいため、結果としてリスクを避け、安定を志向する姿勢が強まります。
失敗を許容しない風土
製造業の現場は「品質第一」であり、失敗が即コスト増や顧客クレームにつながります。そのため若手は「失敗しないこと」を最優先に行動し、挑戦や改善提案を控える傾向に陥ります。こうした風土は一見合理的に見えますが、結果として若手の成長機会を奪い、組織全体の変革力を弱めています。
キャリアの画一化
「配属先で経験を積み、年次に応じて昇進する」という一本道のキャリアモデルが今も主流です。このため、若手社員が自らのキャリアを多面的に設計することは難しく、キャリア自律が育ちにくいのです。多様なキャリア選択肢を示せなければ、若手は「この会社に未来が見えない」と感じやすくなります。
ロールモデル不足
挑戦的なキャリアを歩んだ先輩や中堅社員が少ないと、若手は「自分も挑戦できる」というイメージを持てません。実際、厚労省「若年者雇用実態調査」では、若手が「キャリア形成に不安を感じる要因」として「将来像が描きにくい職場環境」を挙げています。挑戦の成功例を示すロールモデルの存在が、組織文化の醸成に大きく影響するのです。
この課題を改善せずに放置した場合、以下のリスクが現実化します。
挑戦しない若手が増え、イノベーションが停滞
若手が現状維持にとどまれば、新規提案や改善活動が減少し、製造現場から創意工夫が失われます。これは中長期的に競争優位性を失う要因となります。
キャリア迷子のまま中堅化し、受け身の管理職が増加
主体性を欠いた若手がそのまま年次を重ねると、自律性の乏しい中堅層・管理職が増えます。指示待ち文化が強まり、組織の推進力が失われます。
グローバル競争に対応できず、成長が鈍化
世界市場では新技術やビジネスモデルが急速に進化しています。若手が挑戦を避ける文化のままでは、変化に適応できず、競合他社にシェアを奪われるリスクが高まります。
短期的には見えにくくても、5年・10年単位で見たときに企業の存続を左右する問題であることは明白です。
若手の挑戦とキャリア自律を引き出すには、「仕組み化された支援」 が不可欠です。
キャリア面談の実施
年1〜2回のキャリア面談を通じて、若手自身に「どんな挑戦をしたいか」「どんな強みを伸ばしたいか」を言語化させます。こうした場を制度化することで、若手の潜在的な意欲を可視化し、配置・育成計画に反映できます。
越境・異動機会の提供
他部署・海外拠点・新規事業といった異なる環境での挑戦機会を用意することは、若手のキャリア自律を育む有効な手段です。経験の幅を広げることで、視野の拡大と自己効力感の向上が実現します。
挑戦を評価する制度
成果だけでなく「挑戦そのもの」を評価項目に含めることが重要です。失敗を恐れずに行動できる文化を醸成することで、若手は安心してチャレンジでき、組織全体の活力が高まります。
これらの施策は単独で効果を発揮するだけでなく、技能継承の仕組み化と連動させることで、挑戦とスキル獲得が同時に進む「学びの好循環」を生み出します。
事例①:大手製造業 M 社
M 社では「若手が与えられた業務しかしない」と課題視されていました。そこでキャリア面談制度を導入し、若手に挑戦テーマを設定させました。人事部門が研修や異動を支援した結果、新規改善提案件数は前年比2倍に増加。若手社員のモチベーションも大きく向上しました。
事例②:製造大手 N 社
N 社では、若手がキャリアに閉塞感を抱き、離職が増加傾向にありました。越境学習制度を導入し、外部研究開発プロジェクトへの短期参加を可能にしたところ、参加者のキャリア意欲が顕著に向上し、新規事業提案を自発的に行う社員が増加しました。
これらの事例は、「挑戦を後押しする制度」が若手のキャリア自律を生み、イノベーションを加速することを示しています。
キャリコンサロン製造業界超雑談会
製造業の人材育成・キャリア支援をテーマに開催。現場のリアルな声を共有しました。
レポートはこちら
“個別相談会”を開催(まずはお気軽に)
「自社だと何から手を付ければいい?」「用語の意味は分かったけれど、運用に落とすイメージがまだ…」という方へ。
HRラボでは1社ごとの個別オンライン相談(30〜45分)を承っています。建設はもちろん、製造・医療・IT・サービスなど、どの業界でもご利用いただけます。
専門用語の整理から、現場のモヤモヤの言語化まで丁寧にお伺いします。
<お問い合わせフォーム>
下記よりお申し込みください。担当より日程候補をご連絡します。
HRラボ お問い合わせフォーム
製造業大手における「若手の挑戦不足」「キャリア自律欠如」は、年功序列・失敗を許容しない風土・キャリアの画一化・ロールモデル不足といった構造的課題が背景にあります。
しかし、キャリア面談・越境学習・挑戦を評価する仕組みを整えることで、若手は「自らキャリアを描き、挑戦する人材」へと変わります。これは単なる人事施策ではなく、企業の持続的成長とイノベーション創出を支える経営戦略そのものです。
未来を支えるのは、受け身ではなく、自律的に挑戦を重ねる“挑戦する若手”です。製造業の競争力を維持・強化するためには、この変化を制度と文化で後押しすることが不可欠です。
1

2

3